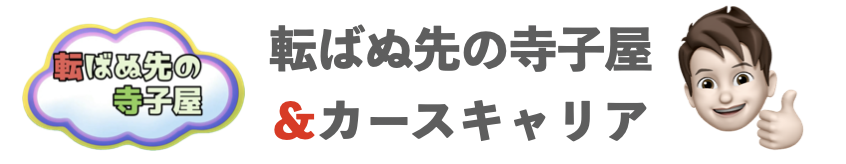みなさん、こんにちは。
転ばぬ先の寺子屋、塾長:ふみちゃんです。
インバウンドも少し落ち着き、日本の各観光地も、いっときの休息かもしれません。
しかし、すぐに、春夏の繁忙期を迎えることになります。
今回は、インバウンドによるオーバーツーリズム課題について取り組みました。
スポンサーリンク
メリットだけではない!
日本の観光地に多くの外国人が押し寄せるオーバーツーリズム、単に、海外の観光客が増えて旅行がオーバー気味だというだけではありません。
そこから、生み出される地域への悪影響も含めて、つまり、メリットだけではなく、デメリットも考慮してオーバーツーリズムを考えなければなりません。
それではデメリットとは、どんなものがあるのでしょうか?
住民は、どんなデメリットを感じているのか、ある調査結果を示します。
住民が感じているデメリット、第一位は、観光客のマナー違反が迷惑ということでした。
では、どんなものがあるかというと、タバコのポイ捨て、食べ歩き、交通ルールの違反や無視などでした。
第2位は、バス電車などの混雑、第3位は、旅館などの観光施設や周辺施設の混雑ということでした。
このように、オーバーツーリズムのデメリットは、その地域に住んでいる住民の数より観光客の数の方が増えてしまうことによって起こります。
したがって、住民の使っていたバスやタクシーは、満員で乗車できない、救急車の出動が増え住民に対応ができない、ホテルや旅館などがいっぱいで予約できない、コンビニから商品がなくなってしまう。
犯罪も増える、などなど、平穏だった住民の生活が脅かされることになります。
オーバーツールリズムの現状と対策
それでは、住民に対してどの程度、観光客が増えているのかみていきましょう。
数年前の環境庁の調査によると、年間で、住民より観光客が多い都道府県ベスト3は、第1位京都で、約4倍、2位は千葉県で約2倍強、3位は沖縄で約2倍弱となっています。
ピンポイントとで見ると、もっとたいへんで、例えば、スキーシーズンの白馬では、住民約9千人に対して、観光客が200万人以上に達しているということです。
このような状況に対して、閑散期と繁忙期もあるので、バス便を増やしたり、救急車の台数を増やしたりできないのが現状です。
対策としては、まずは、観光客への啓蒙活動があります。
旅行前の説明会で日本の文化を学んで来日してもらう。
また、外国観光者のサービル料金を高くして、得られた収入で、インフラ整備や交通整理に充てるなどの対策があると思います。
いずれにしても、メリットの大きいインバウンドだけに、避けるのではなく、デメリット対策をしっかりして、観光客を向かい入れたいと思います。
動画でも詳しく解説
今回は、オーバーツーリズムについて取り組みました。
特に、旅行関係の仕事をしたい方は、深掘りしてみてください。

今回は、以上です。また、お会いしましょう!
スポンサーリンク