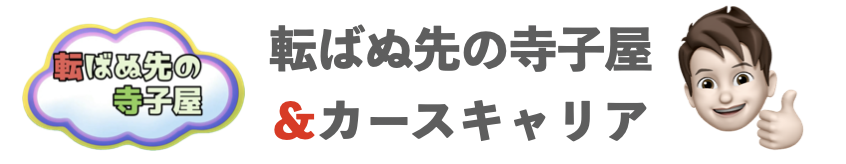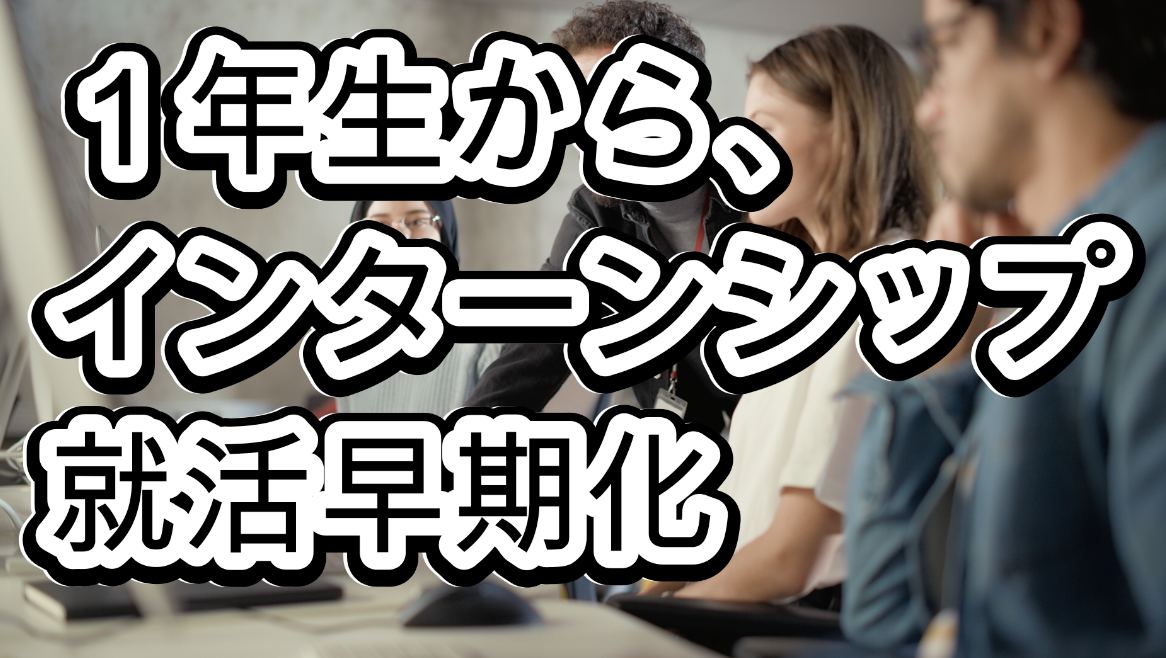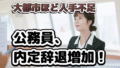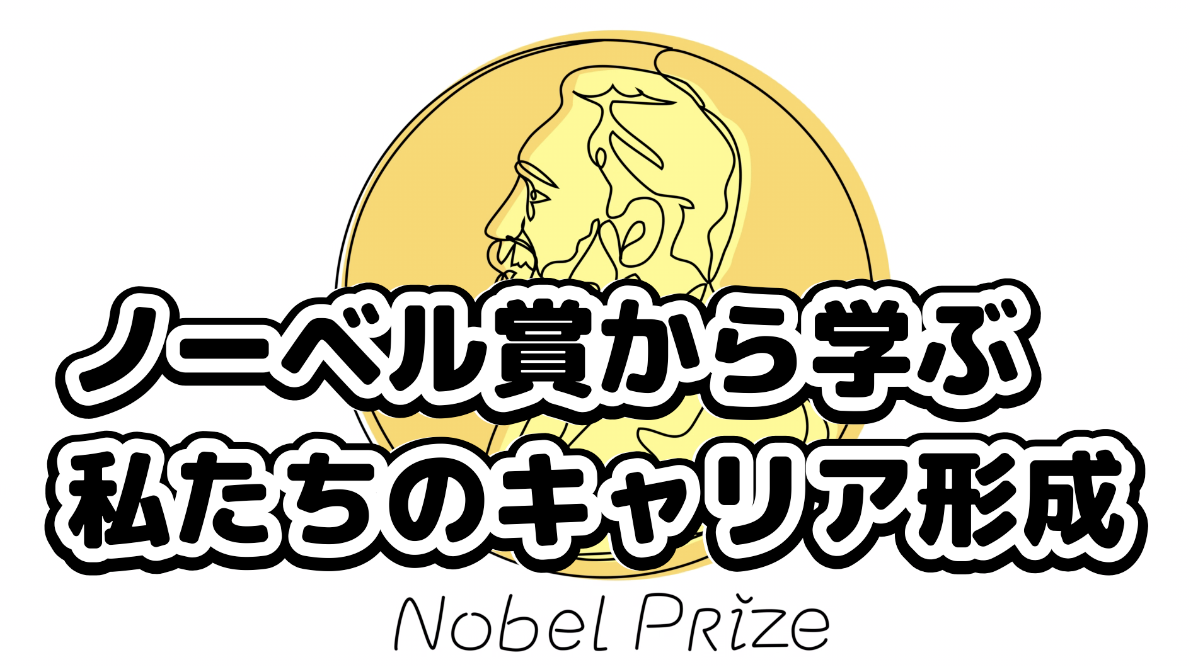みなさん、こんにちは!
転ばぬ先の寺子屋、塾長のふみちゃんです。
米国では、大学1年生の時から、インターンシップに参加する学生が増えています。
インターンシップの早期化が進んできています。
背景には、AIの発展で、初級レベルの仕事が奪われる不安などがあり、早い時期から、社会を知っておきたいことがあります。
日本でも、インターンシップの早期化は顕著です。
今回は、インターンシップの早期化に取り組みました。
!:インターンシップ早期化〜米国就活事情
2:日本の事情
3:動画でわかりやすく!
スポンサーリンク
チャージ(プリペイド)式WiFi!契約・月額・契約期間無し【ネオチャージWiFi】インターンシップ早期化〜米国就活事情
米国では、大学生になってすぐに、15%の学生がインターンシップに応募しているとのことです。
上級生たちが、就活で苦戦している姿を見て、不安に思っているとのこと。
親もその早期活動を陰ながら支援しています。
新入生たちが不安に思っていることは、授業や寮生活だけではなく、将来の不安もあります。
AI(人工知能)の発展で、新入社員の初級レベルの仕事が、AIに奪われるのではないかとの不安です。
そのような不安から、早い時期からインターンシップに応募し、社会や就職先を理解しようとする動きが活発化しています。
今までは、3年生後半にインターンシップに応募するのが一般的でした。
しかし、最近では、1年生の時から将来を見据えて、社会と関わろうとする就活の早期化が進んでいます。
日本の事情
日本においても、就活の早期化は進んでいます。
1年生から内々定を出す企業も現れました。
弊社のインターンシップでは、20年前から春と夏に実施していますが、2025年夏期までに1,230名の学生さんが参加されました。
春期のインターンシップは8割が1、2年生で、夏期インターンシップは、8割が3年生になっています。
累計では、1230名のうち、約500名強が1、2年生の参加になっています。
日本のインターンシップの場合は、仕事体験というよりは、社会体験の様相が強くて、必ずしも、その企業に入社するといったことは少なく、就活の入口のような意味合いが強いようです。
一言で言うと「無償の社会体験」といったことになると思います。
今までは、企業と大学で話し合って決めていた就活ルール(就職協定と言いますが)がありました。
会社説明会を始める時期と面接をスタートさせる時期を、ルール化していました。
3年生の8月にインターンシップ、3月に会社説明会、4年生の6月に面接スタート、10月に内定式といった流れです。
そのルールも、現在は、ほぼなくなり、就活の早期化が進んでいます。
それに伴い、最近では、内々定の乱発が起こっています。
その流れに乗るためにも、低学年から、学業に影響しない程度に、インターンシップなどの社会体験などに参加する学生が増えてきています。
就活は、3年の後期から始めるから、社会との触れ合いも3年からで良いと言うのは古い考え方になりつつあります。
低学年から社会体験を始める学生が、どんどん増えてきています。
ただし、学業を疎かにしないこと、単位は、早めに取っておくことが勧められます。
とにかく、環境変化をしっかり捉え、自分のペースで活動することが大切です。
今回は、インターンシップの早期化に取り組みました。
動画でわかりやすく!
スポンサーリンク